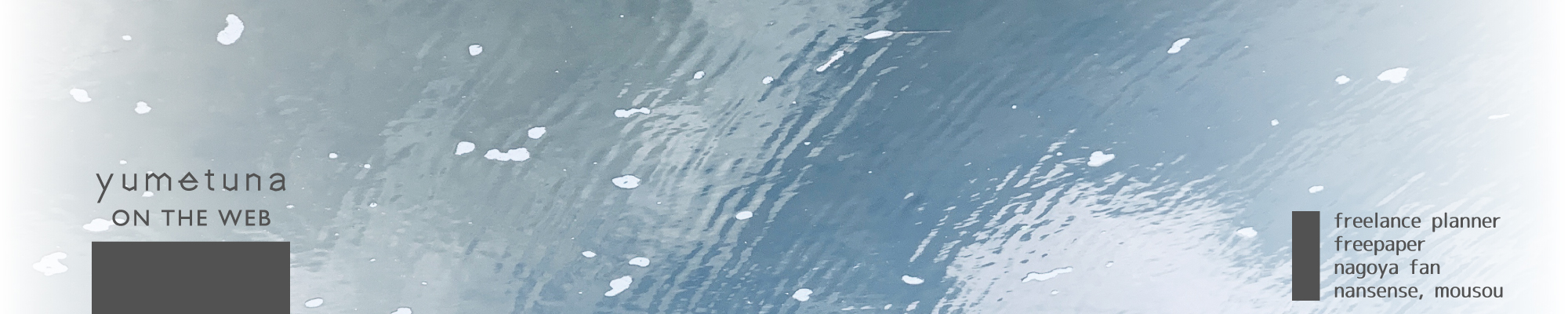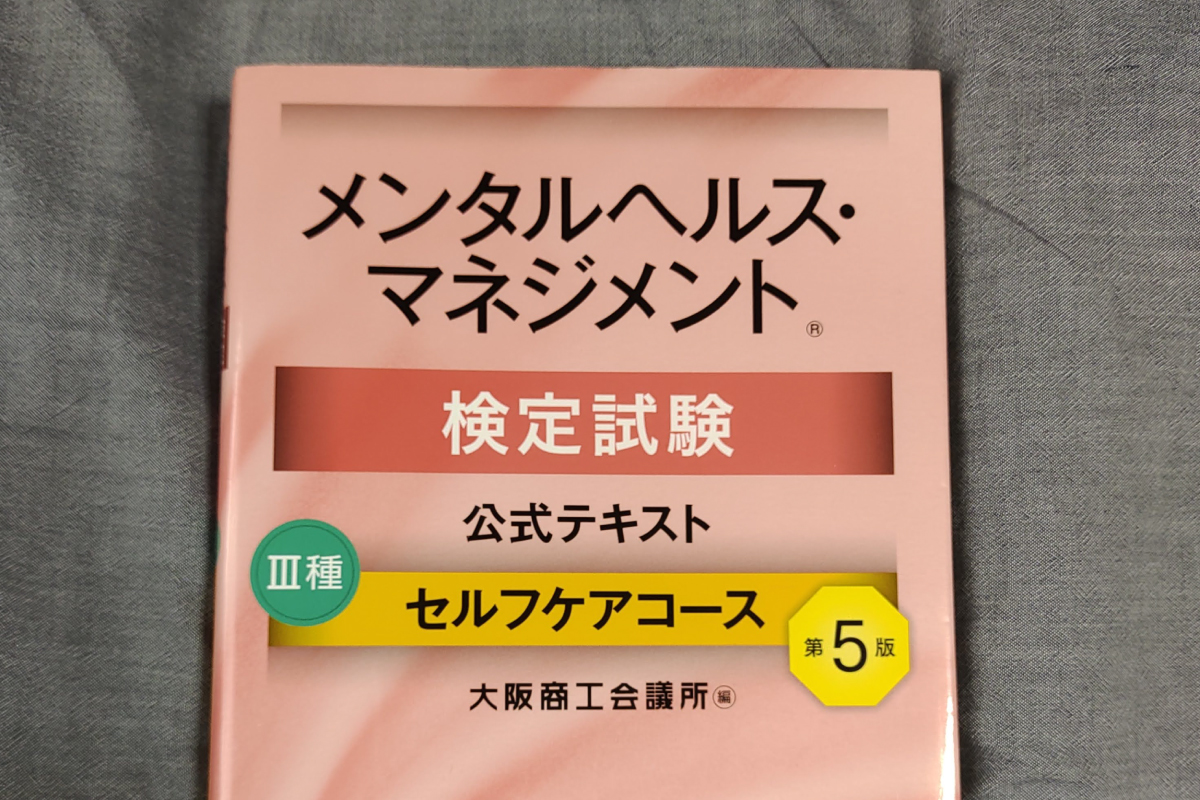1年ほど前に、メンタルヘルス・マネジメント検定を受けて合格しました。
当時、弟が脳の病気になり、その対応に追われて心身ともに調子を崩していました。
過去にも自分自身がメンタルを崩したことがあったり、職場でも若者が苦しんでいたりしている中、自分に何かできることはないかと知らべてこの検定を見つけました。
メンタルヘルス・マネジメント検定では、心の健康管理について学べます
みなさん、メンタルヘルス・マネジメント検定ってご存知でしょうか?
働く人の心の健康(メンタルヘルス)の管理のしかたや、ストレスへの対象法を学べるものです。
仕事や職業生活に強い不安や悩み、ストレスを抱える人は増加傾向にあり、心の不調による休職や離職もまた増加しています。
公式サイトより
働く人たちがその持てる能力を発揮し、仕事や職場で活躍するためには心の健康管理(メンタルヘルス・マネジメント)への取り組みが一層重要になってきました。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は、働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得していただくものです。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験には3つの種類があります
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は、職位・職種別(対象別)に3つのコースがあります。
| コース | Ⅰ種(マスターコース) | Ⅱ種(ラインケアコース) | Ⅲ種(セルフケアコース) |
| 対象 | 人事労務管理スタッフ、経営幹部 | 管理監督者(管理職) | 一般社員 |
| 目的 | 社内のメンタルヘルス対策の推進 | 部門内、上司としての部下の メンタルヘルス対策の推進 | 組織における従業員自らの メンタルヘルス対策の推進 |
対象者が違いますね。私が受けたのは、【Ⅲ種 セルフケアコース】です。
勉強は本とYOUTUBEでしました
Ⅲ種の合格率は70%と知っていましたが、心配性の私は30%も落ちるんだと正直ビビっていました。
私の場合、記憶力が若いときから弱く、一夜漬けのような勉強ではとても無理だと思っていました。
そこで、通信講座を探して、それを受けることにしました。会社から補助がもらえることもあり、決めました。
まずは、公式テキストを読み、模擬テストを解きます。
通信講座のサイトからテストを受け、そこで結果も見れます。
間違えたところを中心に復習。
公式テキストを読み、ポイントをメモしながら、教科書に付いていた過去問題も解きました。
また、並行してYouTubeで「メンタルヘルス・マネジメント検定」の勉強の仕方を動画にしている方がいて、それも観ました。
YouTubeの動画はかなり役に立ちました。
弟の面倒をみながら、仕事もしつつ、よくやれたなあと振り返って自分を褒めてます(笑)。
試験は名古屋の会場でうけました
私は名古屋駅近くの会場で試験を受けました。

けっこうな人が来ていました。
エレベーターで上がり、会議室へ入ります。
試験官の方から説明を受け、試験が開始。
終わった人から帰ってよい感じでしたが、私は回答に迷っていたので、ギリギリまで粘りました。
結果は後日インターネットで確認。
無事合格しました(良かった〜)。
メンタルヘルス・マネジメント検定の公式テキストの目次を挙げておきます
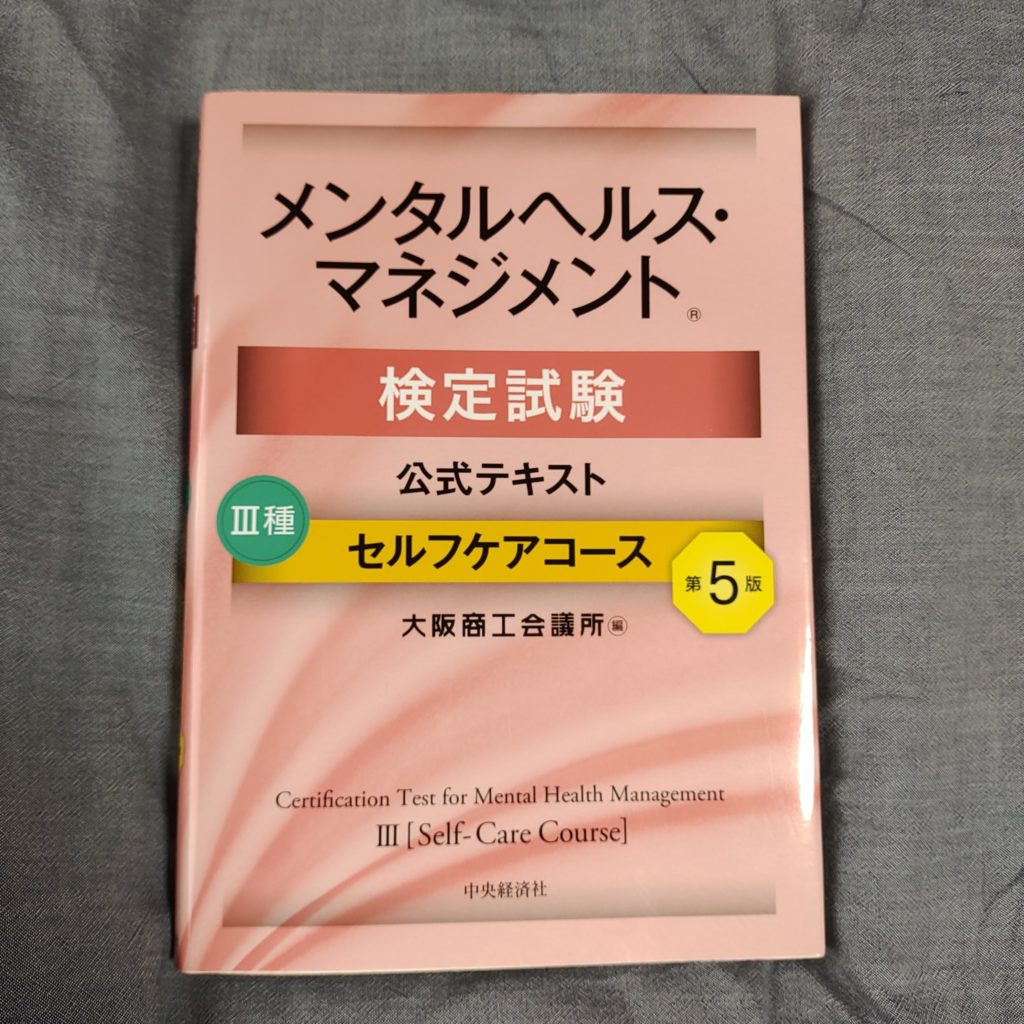
公式テキストにどんな内容が載っているか、気になる方がいるかもしれませんので、目次を挙げておきます。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験 公式テキスト 【Ⅲ種 セルフケアコース】 第5版
第1章 メンタルヘルスケアの意義
1 労働者のストレスの現状
1-1 労働者のストレスの現状
1-2 メンタルヘルスケアの意義と重要性
1-3 メンタルヘルス指針とセルフケア
2 メンタルヘルスケアの方針と計画
2-1 メンタルヘルスケアに関する事業者方針の意義
2-2 心の健康づくり計画
第2章 ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
1 ストレスの基礎知識
1-1 ストレスとは
1-2 ストレスによる健康被害のメカニズム
1-3 産業ストレス
1-4 ライフサイクル、女性労働、雇用形態とストレス
1-5 ワーク・エンゲイジメント
2 メンタルヘルスの基礎知識
1-1 メンタルヘルス不調
3 こころの健康問題の正しい態度
3-1 こころの健康問題は自分とは関係ないという誤解
3-2 睡眠を削って残業をがんばるのは美徳という誤解
3-3 その他の誤解とその対策
第3章 セルフケアの重要性
1 過重労働の健康への影響
1-1 過重労働の背景と労働者の健康状態
1-2 過重労働の健康影響メカニズム
2 自己保健義務とは
2-1 自己保健義務を果たす具体的な行動
2-2 事業者による安全配慮義務と労働者による自己保健義務
3 早期対処の重要性
3-1 自己管理としての早期対処
3-2 事業場内システムによる早期対処
第4章 ストレスへの気づき方
1 注意すべきリスク要因
1-1 注意すべきリスクとは
1-2 どんなリスクがあるか
1-3 ストレスの個人差
2 仕事以外でのストレス
2-1 個人生活におけるストレス
2-2 さまざまなトラブル
3 いつもと違う自分に気づく
3-1 身体面の変化
3-2 行動面の変化
3-3 心理面の変化
3-4 いつもと違う自分に気づく
4 ストレスのセルフチェック
4-1 簡易チェックリスト(職業性ストレス簡易調査票)
4-2 結果の出し方と注意点
4-3 定期チェックの重要性
第5章 ストレスへの対処、軽減の方法
1 ストレスへの対処、軽減の方法
1-1 ストレスの軽減方法
1-2 ストレス緩和要因の充実
1-3 ストレス要因への対処法
2 自発的な相談の有用性
2-1 コミュニケーション・スキル
2-2 話すことの意味(カウンセリングの効果)
2-3 同僚のケア
第6章 社内外資源の活用
1 活用できる資源
1-1 事業場外資源と事業場外資源
2 専門相談機関の知識
2-1 医療機関の種類と選び方
2-2 受診を決めるポイント
2-3 治療の実際
※もし勉強する方は、最新のテキストで勉強してください(法令の見直しや、最新データ、社会情勢などで内容は変更されています)。
試験に合格するのがゴールではないですね
会社ではメンタルを落とす原因が色々あります。
なんとなく時代性もあるような気がしています。
これまでの会社とか仕事とかのあり方と、働いている人の価値観のギャップのような。
最近ではコロナの影響もありますし。
私は弟の病気をきっかけに勉強して試験を受けましたが、今後は自分自身や周囲の人に役にたてるように勉強を続けていきたいと思います。
もし、ご興味がありましたら、メンタルヘルス・マネジメント検定を受けてみてはいかがでしょうか。